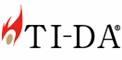みんなで楽しもう!
~琉球沖縄に伝わる民話~
新・口碑伝説民話集録
『琉球民話集』より、第33話
命名式
琉球沖縄では、古くからの習慣として命名式がありました。現在では、殆ど見られなくなりましたが、次のような命名式の風習が近世まで残っていました。
お産のことを琉球沖縄では、しらふじょーと言い、女性の月のもの、あかふじょーとは区別していました。
久高島はじめ、子どもが生まれると河下という、親も子も川で水浴びし、全身を清める習慣が残っていましたが、近年では出産で出た汚れ物を洗うことでその代わりとするようになりました。
ある河下の時、母親が生まれた子どもを河辺の草叢に寝かせ、着物を軽く被せると、その上を小さな蟹や、バッタが、その上を這い回ったため、命名式にそれが風習が取り入れられました。
子どもが生まれると、箕を庭の東方に立て、平草という柴をお供えし、袴を被って子どもを抱き、子どもの成長を神に祈ります。それから桑で作った小さい弓で、箕に向って、三度、矢を射ってから家に入り、子どもに着物を軽く被せてから、小蟹かバッタを這わせます。
それから生まれた子の名を呼び、これで初めて正式に名前が決まりました。
なお、玉城辺りでは、この地方の習慣でその時にこう唱えます。
「莫迦になるな、勝れるな。」と。
そう言って、赤児の額を水で撫でる風習が残っていました。これには、中庸(※偏ることなく、常に変わらず、過不足がなく調和が取れた)の人物になれという意が込められているそうです。
※注や解説
【河下】~川下り。
【桑で作った小さい弓】~桑の弓で箕を射る風習は、日向の宮崎地方にもあり、弓を射ることを「生後七日目の名付祝」と言い、今でも残っているそうです。首里方言に、産むことを「しらすん」「しでゆん」があり、本土では産に「すで」という古語があるため、古代日本語との繋がりがよく指摘されます。
【玉城】~玉城の以前の発音は「たまぐすぃく/たまぐしく」など。
Copyright (C) 横浜のtoshi All Rights Reserved.